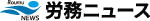あと3ヶ月で今年度も終わりを迎えますね。新年度になればどこの会社にも新しい社員が入ってきますが、社員教育に関するご相談は当社にも非常に多く寄せられます。
「今度新しく来た人、全然使えないからクビにしたいんだけど…」
「せっかく新しく雇ったのにどんどん辞めてしまう。先輩が怖いらしいんだよね」
という話をたくさんいただきます。
そうなると必ず教育の話になりますが、ここで発生するのは「何回も言ってるんだけど伝わらない」という問題です。
結局のところ何回も言うしか解決策はありませんが、それでもある程度は伝わりやすく、効果が出やすい教育の5ステップをまとめてみました。
なお、偉そうに記載していますが、すべて過去の素晴らしい経営者や指導者からのパクリなので、ある意味安心していただければと思います。
社員教育のための5ステップ
①働く意味の設定
何といっても重要なのは、なぜ働くのかを明確にすることだと思います。
ほとんどの人間は、生活のために仕方なく働いているのではないでしょうか。私自身も、もし生活のためのお金が必要なかったら働かないかもしれません。
しかしそのような心持ちでは、前向きに成長しよう、働こうというマインドを引き出すことは難しいはずです。
さらに人間は、やる意味がわからないことには力が出せません。
誰もが子供の頃、学校の先生に怒られたとき「はぁ?何の意味があるんだよ、それ」と思ったことがあるのではないでしょうか?
つまり最初にやるべきことは、なぜ働くのかの設定です。
もっといえば、なぜ「一生懸命」働くのかの設定ではないでしょうか?
当社では入社した社員に、この設定を最初に考えてもらっています。
ここでよくあるのは「生活のために」だったり「勉強したい」だったり、
失礼ながら将来の解像度が低いように思います。
私たちは現代社会において、おそらくですが80歳、場合によっては90歳、100歳まで生きる可能性があります。
そんな将来に向けて「どういう生活をするのか」「そのときにどんな仕事をするのか」。
そのためには5年後、あるいは10年後にどんなことを知っていなければいけないのか。
成長が必要であれば、成長するために日々何をしなければいけないのか。
それに向けて、どんなマインドで仕事に臨まなければいけないのか。
そういった今の仕事が未来につながることを、いかに解像度を高く設定できるかで、最初のマインドセットが決まります。
なお「成長したい」と言う人が多数いますが、この場合は「成長とは何なのか」を定義したほうがいいと思います。
「何がどうなったら成長したことになるのか」と聞いても、回答がないケースは結構あります。
当社では「昨日できなかったことが今日できるようになること」を成長と定義しています。
②目的とミッションの設定
働く意味、目的が設定できれば、その次は与えられた役割での目的とミッションを定義するべきです。
組織の中で働くので、その与えられたポジションでの目的を理解していただき、そこに向けて日々の業務を行う必要があることを理解してもらいましょう。
このポジションごとの目的設定は非常に重要だと思います。
たとえばブロックを積んで壁を作る仕事があるとしましょう。
この仕事に取り組むとき
- ・ブロックを積むのが仕事だと思っている人
- ・ブロックを積むことで、壁を作るのが仕事だと思っている人
- ・ブロックを積み、壁を作ることで、その壁の向こうにいる人の生活や命を危険から守ることが仕事だと思っている人
どの人が最も良い仕事をしそうでしょうか?
自分の仕事の目的や意味、そして達成するべき未来のビジョンが見えている人は、自然と仕事のクオリティが上がるはずです。
③手順とルールの設定
ミッションを達成するために、業務でさまざまな取り組みを行います。
1人で完結する業務ではない以上は、手順とルールの設定は非常に重要です。
前述の「ブロックを積む作業」でも、作業手順が決まっていなければ協力もできませんし、改善を検討することもできません。
最低限のルールが決まっていなければ、業務のクオリティも担保されません。
与えられたミッションを達成するために、最低限の守るべき手順とルールをしっかり決めましょう。
当社で発生しがちなケースでいうと、業務を引き継ぐときに「どこまでやったかわからない」ということがまぁまぁ起きます。
これは、作業手順・作業工程が決まっていないことで発生する問題です。
「1~5の工程のうち3まで終わっています」
これが共通認識として伝わるような体制を目指していくべきだと思います。
④改善の意識醸成
職種によるかもしれませんが、一般的には②で決めた目的やミッション達成のために、日々の業務改善は欠かせません。
業務改善といっても、作業工程やルールを見直すようなものから「もっと〇〇を勉強する」という個人的なものまで、さまざまな改善事項が発生するはずです。
この改善意識を醸成させることは非常に重要だと考えていますし、改善の繰り返しが成長につながっていくと当社では考えています。
しかしこの改善作業は、現状を変化させるという非常にストレスフルな作業になります。なかなか自発的にできる人は多くありません。
そこで当社では「もっと良くなる会議」と称して、週に一度の会議を実施しています。
この会議では
- ・今週良くなったこと
- ・来週良くすること
以上の2つを発表してもらっています。
これにより業務をアップデートしていくという意識が醸成されていると感じています。
会議では発表に対して
- ・何を目的にそれをやるのか
- ・誰がやるのか
- ・いつまでにやるのか
- ・具体的に取り組めるアクションになっているのか
などを確認しています。
この会議は、教育の場として非常に有効です。
年間52回の改善アクションが発生します。どんどん良くなります!
⑤評価
②~④の取り組みを評価することも重要です。せっかくいろいろ工夫して頑張ってきたのに、何のメリットもないのではモチベーションが続きません。
可能であれば、2種類の評価を実施すべきです。
1つ目は「日々の評価」です。
良い行動には、毎日「承認と感謝」をしましょう。
たとえば「出社する」という行動は、社員が決定して行動した結果です。まずは出社してくれたことに承認と感謝をすることから始めてください。
さらに、工夫や改善へのアクションを承認していくべきです。
褒める必要はありません。
「工夫してるね!」
「考えてるね!」
そんな事実を認めて伝えるだけで十分だと思います。
経営者やマネージャーが日々の工夫や努力について承認しないと、やる気を失い、信頼も失います。
反対に、ルール違反や手順違反は、現行犯で注意するべきです。これらの問題行動を黙認すると、決めたルールが形骸化してしまいます。
目的のためにルールを変えるのは問題ないことですが、基本的にルール違反を認めてはなりません。
ルール違反が発覚した際は、問題行動であることをきちんと伝えて、守れないのであればこのコミュニティーには所属できないとしっかり認識させるべきです。
赤信号を無視する人間がいたら、通常は捕まり、社会から隔離されます。
定めたルールを守らないというのは、上記の例と同じようなことだと伝えましょう。
2つ目は、「報酬に反映する評価」です。
年1回か半年に1回か、会社によって決定して良いと思いますが、一定期間の業務について評価をしましょう。
報酬に対して評価をする上で重要なのは、頑張ったかどうかではなく「自身の目的やミッションの達成につながったか」だと考えます。
よって、評価する内容は数値化できるものであることが理想です。
「店舗の居心地が良くなかったか」というような指標は、もはや評価できません。
それであれば「店舗の再来店率はどうか」という指標のほうが適切です。
「評価のためにどのような数字を用いれば、ミッションが達成したという判定がつくのか」。
これを考えるのは、経営者やマネージャーの腕の見せ所かなと思います。
どちらにしても評価をしないと「やっても意味ねーじゃん」となってしまいますので、絶対評価は必要です!