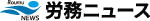雇用契約とは、時間とお金を一定の条件で交換することをお互いに約束する契約だと解釈しています。
日本の労働基準法、および民法の効力下に限定されますが、現在の国内法や裁判例に照らし合わせると、この解釈が正しいのではないかと思います。
時給制・日給制・月給制・年俸制のすべてにおいて、この解釈は変わりません。
時給制なら1時間=○○円となり、月給制なら1ヵ月=○○円となります。
この1ヵ月が曲者です。
1ヵ月というと、いろいろな解釈ができます。
30日間だったり、週休2日として21日だったり、じゃあ土日祝休みはどうなるの?など、解釈の幅が出てきます。
契約において重要なのは、誰が見てもわかることです。
一日の労働時間と休日を明記して、月給に対して〇日間、もっというと〇時間働くのかを明記する必要があります。
これが所定労働時間と言われる概念です。
1日8時間労働で土日祝休みなら、
年間365日-休日119日(土日 各52日、祝日15日として計算)=246日
246日×8時間÷12ヵ月=164時間
となります。
雇用契約書を作る際は、「給与が何時間分なのか」を十分に注意してください。
さらにもう一つ重要な要素は、一定条件で交換するということです。
この条件として最たる例は、出社日や出社時間です。
所定労働164時間だからといって営業時間外に働かれても、雇用者側としては困りますよね?
そのため、時間とお金を交換する条件を定めておく必要があります。
たとえば、8:00~17:00 月~金曜と決まっている場合、その時間以外は時間とお金が交換できません。
ところが最近は働き方も多様化しており、シフト制などの働き方も増えています。
「時間とお金を交換する条件」を明確にすることなく、雇用契約を結んでしまっているケースが散見されます。
これはとても危険です。

シフト制の落とし穴
シフト制を否定するわけではありません。
しかし「週に○日は働く、週に○○時間は働く」など、最低限の条件を可能な限り明確にしておきましょう。
雇用契約が守られなかったときは、約束を破った側にペナルティが課されます。
決まった時間に出勤できない従業員は懲戒解雇になりますし、決まった時間に働かせない会社は、休業手当を支払う義務があります。
また、シフト制のトラブルは、パート契約で多く見られます。
「急にシフトを減らしたいと言われたから辞めてもらいたい」
「一時的に増やしたシフトを元に戻そうとしたら、休業手当を請求された」
「急にシフトを減らされたけど休業手当がもらえない」
といったケースです。
労働時間に関する条件をしっかり明示していないと、お互いに損をすることになります。
私が学生時代に働いていたアルバイト先では、毎週シフトを提出して、自由に決める形式でした。
ただ、雇用契約書では目安が定められています。
「勤務時間は提出された希望スケジュールに基づき、下記の勤務時間数を目安に始業・終業時間を被雇用者の希望を考慮して、1週間前までに決定する
平日〇時間×〇日(〇曜日、〇曜日)
土曜〇時間(〇時から〇時)
日曜〇時間(希望時間特になし)
1週間の勤務時間は上記より、〇〇時間を目安とする
休日:毎週少なくとも1日(〇曜日または曜日指定無し)、その他会社が定めた日」
大体このような書き方だったと記憶しています。
これなら、
「○○さんは決められた時間を働けないので、働くか辞めるか選択してください」と会社からも要求できますし、
「雇用契約で決めた○○時間のシフトが維持されていないので、休業手当を支払ってください」と従業員から要求することもできます。
実は、コロナ禍でアルバイトが休業補償をもらえないという問題が多発しました。
会社は「シフトが減ったんだからしょうがないでしょ」と突っぱねたわけです。
従業員側も最低労働時間が決まっておらず、戦えませんでした。
※もし本当に上記のケースで争った場合、雇用契約書が無ければ、直近の一定期間のシフトから目安を算出するのが妥当です。
これは「雇用者には被雇用者の生活が、著しく損なわれないよう、維持するために努力する義務がある」という考えからだと思ってください。労働基準法の目的にも沿っていると考えられます。
上記のようなトラブルが起きないよう、雇用契約書本来の役目を果たすものを作っていく努力が必要です。
雇用契約書を作成する際は、可能な限り条件を具体化することに気を付けましょう。