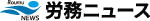本を読むなんて、正直めんどくさい
読書って、めんどくさいですよね。
わかります。
社会人にとって、まとまった時間の確保は至難の業。メール、会議、締め切り…そんな中で読書は後回しになりがちです。
でも、本にはネット検索では得られない「先人の人生をかけた気づき」がギュッと詰まっています。読むだけで、ちょっと賢くなった気分になれる最高の教材なのです。
ネット検索 vs 読書:使い分けがポイント
・検索でカンタンに答えが出るテーマ → ネットでOK
・深い洞察や多様な視点が欲しいテーマ → 本でじっくり
検索で「部下 指示 方法」と打てば大量のノウハウが出てきますが、経験と試行錯誤を積んだ著者の深い考察をまとめて学ぶには、本の力が必要です。特に「コミュニケーション」といった”正解のないテーマ”こそ、本からの学びが非常に効果的だと思います。
社会人の読書習慣化のコツ5選
① 読む時間をスケジューリングする
- ・「この時間に読む!」とカレンダーに組み込んでしまいましょう
- ・予定表に「読書」と書いて、自分を縛るのがコツです
- ・隙間時間を見つけて、その時間を確保することが大切です
② 一気に読むこと&時間内に読み切る
- ・「続きは明日」で後回しにすると、結局先に進みません
- ・決めた時間(例:30分、1セッション)で「読み終えた!」という小さな成功体験を得ると、脳は「またやりたい」と感じます
- ・読む前に「今日はこの範囲を読み切る」と目標を設定し、一気にページをめくり切るクセをつけましょう
- ・おすすめは「この1時間で全部読む」と決めて、一気に最後まで読むこと。一度閉じるともう開きません
③ とにかくページをめくる
- ・面倒くさいときは読まなくてOK
- ・まずはパラパラとめくって、気になった見出しやキーワードだけ立ち止まってじっくり読みます
- ・気軽に「拾い読み」する感覚でOK
- ・完璧主義は禁物。興味のある部分から読み進めましょう。
④ ページをめくったついでに文字も見る
- ・一言一句追うと疲弊します
- ・右から左、上から下へざっとスキャンし、要点だけをキャッチ
- ・気になった一文に出会ったら、そこで深掘り読書
- ・段落の最初と最後を重点的に読むのも効果的です
⑤ 課題を設定して読むこと(RASの活用)
- 解決したい課題があれば、流し読みでも脳が勝手に反応します
- まず「何を解決したいのか」「何を知りたいのか」という問いを立てましょう
例:「チームのモチベーションを上げる方法を知りたい」
例:「業務効率を上げる具体的な方法を見つけたい」
そうすると、脳のRAS(網様体賦活系:Reticular Activating System)が働き、目的に関連する情報だけをキャッチして目立たせてくれます。
・RASは「赤い車を探せ!」と思うと街中の赤い車が目につきやすくなる仕組みと同じ
・本でも”知りたいこと”を最初に設定することで、必要なキーワードやフレーズが自然とアンテナに引っかかり、効率的にインプットできます。
読書は”仕組み化”が命
読書を習慣化するポイントは、
- ・スケジュール化 → 強制力を味方に
- ・一気読み&達成感 → 継続のモチベーション
- ・めくり読み/流し読み → 心のハードルを下げる
- ・目的設定+RAS → 脳を合理的に活用
最初は「めんどくせぇ…」と思うかもしれませんが、この方法を試せば「スキマ時間」で本がどんどん進むようになります。継続は力なり。小さな一歩から始めましょう。