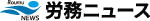「めちゃくちゃ要望ばかり言ってくる社員がいてストレス…」
そんな相談をよくいただくので、対応方法をまとめてみました。
なぜ要望が多いのか
給与アップの要求ばかりしてくる社員=「お金は有限」を理解できていない
多くの社員は、会社の資金に限りがあることを理解していません。給与アップや設備投資などの要望が簡単に通る、と考えていることが多いように感じます。
自己評価が高い=評価に乖離を感じている
自分の会社への貢献度や市場価値を過大評価し、それに見合った処遇を求めるケースです。実際の業績や会社への貢献度と、本人の認識にギャップがあります。
不満を伝えれば、誰かが何とかしてくれると思っている=「ママ、おしっこ」と同じ
子どもが「ママ、おしっこ」と言えば母親が対応してくれるように、不満を表明すれば誰かが解決してくれると思っている幼児的な心理状態です。自己解決能力や当事者意識が不足しています。
対応方法
①要望の確認
要望を具体化して「結局、何をしてくれという話なのか」を明確にしましょう。
「私は頑張ってる」「今の給与がおかしい」などの不満ばかりで、要望が明確になっていないように感じます。
多くの人は不満を伝えてきます。不満を聞いても意味がないので、要望を確認しましょう。
- ・「要は、給与を上げて欲しいってことですか?」
- ・「要は、業務を減らして欲しいってことですか?」
また、ここで大事なのは「いつまでか」です。一回で満足なのか、ずっと続けて欲しいのかを確認します。
不満を言ってくる人は、自分が何を要望しているのかがよくわかっていません。まずは不満を要望に変えて明確にしましょう!
②会社のメリットを確認
その要望を聞いた場合、会社にはどのようなメリットがあるかを考えましょう。
①のように不満ばかり伝えてくる人は「自分の不満は解消してもらえるはず」と思っています。
しかし、本来これは要望ではなく、交渉です。会社は交渉を受ける立場です。交渉を受ける立場として「あなたの要望を聞いた場合に、会社にどんなメリットがあるんですか?」と聞きましょう。
メリットがあれば要望を検討する、メリットがなければ検討しない。
至極シンプルな話であると、相手に理解してもらうといいでしょう。
また「なぜそう思うのか」みたいな議論は避けるべきです。
この時点では、会社は交渉を受ける立場であり、理由の正当性などは関係ありません。理由に説得力があったところで、会社にメリットがなければ交渉を受ける人はいないと思います。
そしてメリットがなければ、はっきり断りましょう。「会社にメリットがないのでお断りします」と言いましょう。交渉を一回終わらせないと次にいけないので、まずは着地を意識しましょう。
③背景の確認
要望を持ってきた背景を聞いてみましょう。ここで、交渉から相談に切り替えます。
もし社員が困っているのであれば、一緒に解決策を模索するべきです。
- ・業務負荷が重くて困っている
- ・実はもっと収入を上げないといけない理由がある
こういった悩みを持っている場合は、解決策が間違っているだけなので、一緒に解決策を考えるのが重要です。
問題意識がある人は、成長します。正しい成長方向を伝えられると、今後戦力になる可能性が十分あります。
問題があるわけでなく「ただ不満」というだけであれば、放っておいていいでしょう。会社は社員の不満を解消するために存在するわけではありません。
要望対応チェックリスト
1.要望を具体的に言語化させる
2.期間・頻度を確認する
3.会社側のメリットを確認する
4.メリットなし→丁寧に断る
5.背景に真の問題あり→問題解決の相談に切り替える
6.単なる不満→聞き流す
補足事項
対応時の心構え
・感情的にならず、冷静に対応することが重要です。相手の態度に引きずられないよう注意しましょう。
・話を聞く際は、腕組みなどの防御的な姿勢は避け、話しやすい雰囲気を作りましょう。
・要望を明確化する質問は、否定的なトーンではなく、理解を深めるためのものだと伝えましょう。
記録を残す
・要望内容とその対応結果は、必ず記録に残しておきましょう。特に繰り返し要望してくる社員の場合、過去の対応履歴が役立ちます。
・「前回はこういう話をして、こういう結論になりましたね」と振り返ることで、同じ議論の繰り返しを防げます。
・要望を聞くときは、相手の要望とこちらの質問を文書化しながら話すと「そんなつもりじゃなかった」みたいな不毛な議論を避けられるので、ぜひやりましょう。
組織全体への対策
・個別対応だけでなく、組織全体の仕組みとして、定期的な面談や業績評価の機会を設けて、要望が溜まりにくい環境を作りましょう。
・評価基準や報酬体系を明確にし、透明性を持たせることで、根拠のない要望を減らせます。
成長機会の提供
・単なる要望者を、問題解決者に変えるよう促しましょう。
・「その課題、自分で解決してみませんか?成功したら評価します」と提案することで、当事者意識を育てられます。
・能力開発やキャリアパスの相談に切り替えることで、建設的な対話に転換できることもあります。
退職を考慮する
・何度対応しても改善されない、会社の方針と合わない要望を繰り返す場合は、お互いのためにも退職を検討したほうが良いケースもあります。その場合は、本人のキャリアを考えた丁寧な対応を心がけましょう。