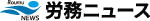個人的に「○○ができたら、給与が上がる」のような制度に違和感を持っています。
もし「勉強したらお金をあげるよ」という人が存在したらいいのですが、残念ながら今のところ会ったことはありません。
というか、お金を払って勉強する人がいる一方で、勉強したからお金をくれという人もいるというのは、世の中はとても複雑だなぁと感じます。
話が逸れましたが、つまり、何かができるようになっただけでは給与を上げるのは難しいということです。
「新たにできるようになったことで、もっと稼ぐ」が重要な観点になります。
また、給与に対しての納得感は大事だとも思っています。
私も気が小さいので「当社のみんなはどう思っているんだろう、、」と内心ドキドキです。
現段階での私の「給与についての考え方」を下記にまとめました。
①給与=人への事業投資
私は給与を事業投資として考えています。
会社と社員は「人的資本=自分」と「経済資本=お金」を交換する関係です。
交換といっても、成果報酬ではありません。
「売上が上がったら分配します」のような成果報酬型だったら入社しませんよね。
それに成果報酬型でやるなら、売り上げが下がったら給与を減らさないと潰れてしまいます。
給与は前年度の成果報酬ではなく、今年度の期待値に払う=未来への投資として考えています。
簡単にいうと「300万払えば900万になって返ってきそう」ということです(この約3倍という設定は私の個人的な決めごとです)。
当社を例に挙げますと、
- ・設備やシステムなどへの環境投資
- ・知的サービス提供のための、知識の仕入れ
- ・コロナのような不測の事態に備える利益の貯金
など、事業をしていく上で必要な各種要素を勘案して、おおむね30〜40%が人に投資できる分と決めています。
当然「900万返ってくるなら450万払うよ」という会社もあるかもしれません。
ただし通常は、事業の拡大スピードや、経営の継続性、環境など、何かしらの要素とのトレードオフとなるはずです。
まとめると、皆さんは自分のために投資を引き出す「事業者」であり、
会社は回収見込みの高そうな事業者にお金をあげる「投資家」です。
人は可能性に投資します。
投資を受けるなら可能性を感じさせる必要があるということです。
②市場価値=希少性
我々はいつでも、どこにでも仕事を変えることが可能です。
つまりオープンで開かれた市場にいます。
そのため、希少性=レア度が重要な価値の源泉にもなります。
他に代替が利かないような人なら、投資回収率が低くても市場から求められます。
つまり、
300万払って900万回収できる人より
1000万払って2000万回収できる人
のほうが市場価値が高いということです。
もしくは「この人がいないとビジネスが成り立たない!」ということなら「プラスマイナス0でも雇いたい」という場合もあるでしょう。
また、希少性にはプラスの意味とマイナスの意味があります。
「500万払ったら1000万になるけど、コミュニケーションがめちゃくちゃ面倒臭い人」はマイナスの意味での希少性を発揮しており、通常は要らないと判断されます。
レアなだけじゃダメということですね。
プラスの方向に希少性が高い場合は、魅力が高い=投資を受けやすいということになります。
③自分の人生は自分で叶える
会社と社員の関係性は、我々の本業である「社労士事務所とクライアント」の関係と本質的には一緒だと思います。
我々は
「これぐらい費用をいただければ承ります」
「その費用ではお引き受けできかねます」
「この作業をこうしても良いでしょうか」
「この作業はそもそも必要なのでしょうか」
「これもやらないとダメですよね」
というような交渉をしつつ、業務を請け負っています。
つまり、雇われる側も交渉しないといけないということです。
私も当社の社員の皆さんから、昇給を交渉してもらうのも良いかなと思っています(お互いにまあまあ疲れる作業ではありますが)。
ただ、業務に支障をきたすので、毎日言われても困ります。
そこで毎年4月に向けて、交渉してもらったら良いかなと。
ここで一つお願いしたいのは
「現在までの実績をもとに、来年度のご自身の期待値を自分で証明して欲しい」ということです。
投資を引き出せるかどうかは、皆さん側にも責任がある=フェアな関係だと思います。
とはいえ、投資するかどうかの決定権は払う側にあるため、完全なフェアとはいきません。
お互いにお互いの望みを自己責任で全うする、という意味でのフェアな関係を目指せれば望ましいのではないかと思っています。