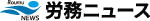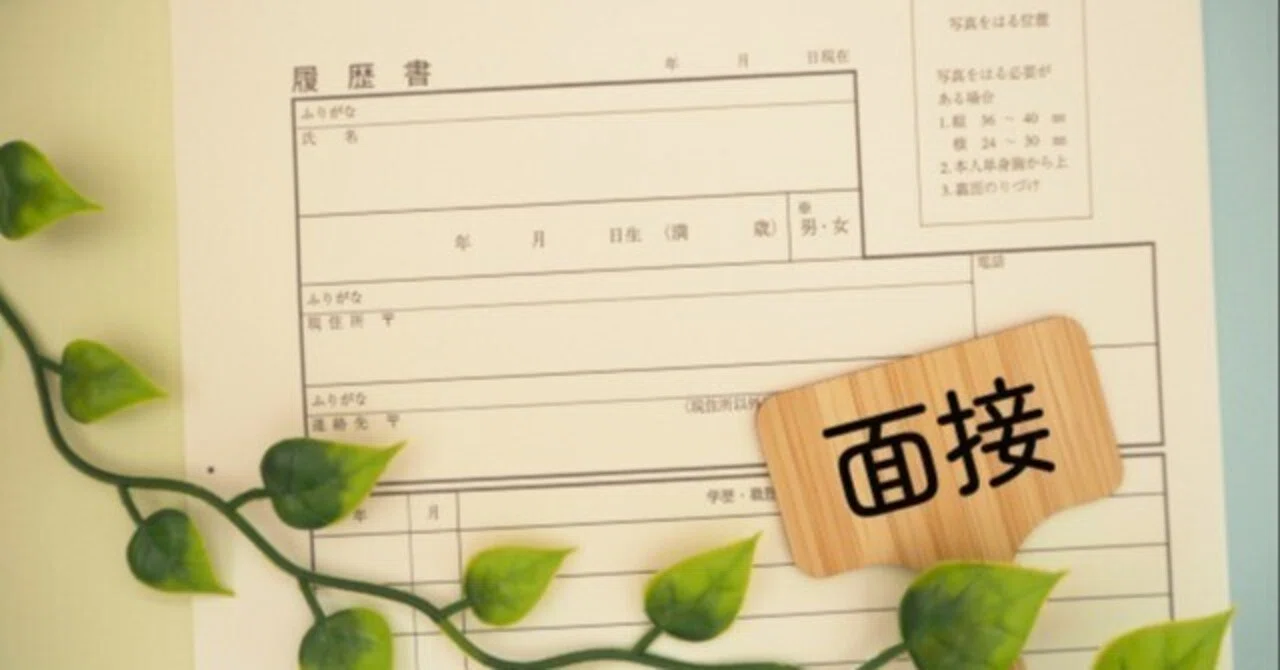最近、面接をたくさんしたのですが、世の中には本当にいろいろな人がいまして。
良いか悪いかはさておき、ある程度はふるいにかけなければなぁと感じています。
と言っても、ダメな人を避けるとは思っていません。
ちゃんと教えていけばある程度は何とかなるはずなので、余裕があったらどんどん入社させるのも良いと思います。
ただ、中小企業の多くが教育にそこまで時間を割けないのが現実です。
そこで、ある程度は教育に割く時間を減らせたり、今後の成長が期待できたりするほうが良いなと考えて「最低限はこういうことを聞くと良いんじゃないか」ということをまとめました。
①「今回はなぜ応募してくれたんですか?求人のどこが特に良かったなどはありますか?」
アイスブレイクも兼ねての質問ですが、話しやすい場にすることと、相手の状況を把握することが大事かなと思います。
いわゆる志望動機と一緒ですが、本音が聞けたほうが良いと考えて、こういう聞きかたをしています。
なお、当社は求人にいろいろ書いてあるので特にどこが気になったのかがわかると重要視していることもわかるため、この質問をしています。
すると、大体は以下のような回答になります。
- ・「この仕事に興味があって~」
- ・「この仕事なら成長できるかと~」
- ・「求人の○○の部分に共感して~」
「なぜそう思ったのか」という理由を含めて深掘りできると良いと思います。
②「今の(直近の)仕事をなぜ退職(転職)しようと思っているんですか?」
中途採用の場合に限りますが、多くの人は何らかの不満などを抱えていて転職を考えているはずです。
ここをしっかり聞いておかないと、入社しても同じことになってしまいます。
ただ、この質問は警戒されるので質問の趣旨を伝えましょう。
「当社に入っても同じような状況になったらお互いに不幸になってしまうので、確認のために聞きました。
正直な理由を言ってくれたほうがミスマッチにならないと思うので、ありのままを教えてもらえるとありがたいです」
と伝えるのが良いと思います。
「うちなら解消できる理由だな」「うちならそういうのは無いな」
と回答できるのであれば相手も前向きになってくれますし、ミスマッチも減ります。
回答としては、以下の4つのどれかになる印象です。
1.何かしらの不便が起きている
休みづらい、通勤が大変、テレワークできたら、というような感じです。
「逆にどういう状況になっていたら、問題なかったですか?」
などと聞いていくと、解消できるかどうかが判断しやすくなります。
2.将来が不安
会社の将来が不安というケースと、自分のスキルアップにつながらないので不安というケースがあります。
会社の将来が不安という場合は「そう感じた具体的なエピソードはありますか?」と理由を聞きましょう。
「うちの会社でも同じだな」と思ったら厳しいかもしれません。
自分のスキルアップにつながらなくて、、という場合は現在→過去→未来を聞きましょう。
現在:「ちなみに今はどんな業務をしているんですか?」
過去:「今の部署の前や、入社したばかりの頃はどんな業務をしてたんですか?」
未来:「あなたより少し先輩の人たちはどんな業務をしてるんですか?」
自分が努力や改善をしないからスキルアップできないケースもありますが、入社して何年経ってもずーっと同じ簡単な業務を続けさせる会社も存在します。
どちらのケースに該当するのかを見極められると良いかなと思います。
3.評価が無い、昇給が無い
頑張っても評価されなくて、、、昇給しなくて、、、というケースです。
「そう感じた具体的なエピソードはありますか?」
「ちなみにどういう業務をしてるんですか?最初は?今後は?それでも上がらないの?」
と具体的に確認しましょう。
これは正当な文句だと思いますので、自社に昇給などの制度がきちんとあれば問題ないのですが、単に承認欲求が強すぎる可能性があります。
4.職場環境が悪い
概ね人間関係に起因する問題です。
お局さんがいるとか、社長や上司がウザいとか、仲が悪いとか、そういうのですね。
「そう感じた具体的なエピソードはありますか?」
「特につらかったエピソードを教えてください」
※「それのどこがつらいの?」と思ったら「それでどんな気持ちになったのかを教えてもらえますか?」と聞いておきましょう。
具体的な話じゃないと「それはひどいな」なのか「それぐらい普通でしょ」なのか判断できません。
③今までの職歴
職務経歴書を事前に出してもらうと質問しやすいので、依頼しておくことをおすすめします。
各職場でどんな業務をしていたのか、誰に、何を、どうやって、なぜ、と一個ずつ飛ばさずに確認しましょう。
ここでの目的は2つあります。
1.応募者のスキル、経験、技術がわかる
具体的な仕事をイメージできるように聞けると、スキル等を把握できます。
2.直近以外の退職理由
②と同じ理由ですが、各職場の退職理由を聞いておくと自社に合うかどうかわかります。
以上、まずは前半戦でした。後半に続く。